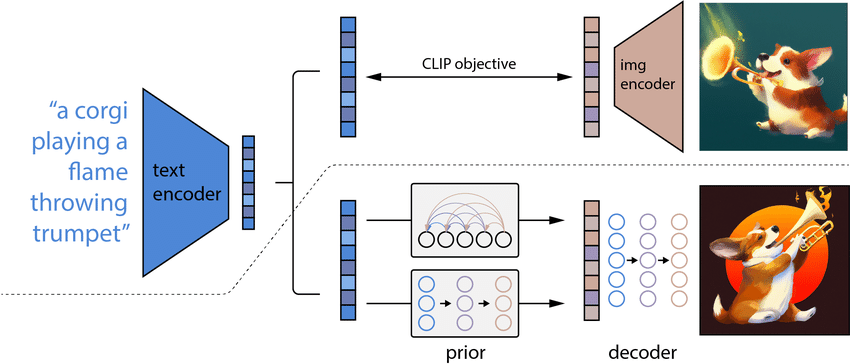Vision Transformer(ViT)[Dosovitskiy 2020]
- Transformerのエンコーダを画像に転用
- 画像をブロック状に切って単語のように扱う(右図)
- 右図のCLS: クラストークン
- 文の分類と同じ
- 全結合層(MLP Head)に通す
- 画像をブロック状に扱うのはCNNと同じだが、CNNは遠くのブロックの関係性を見るのが苦手
画像: CC-BY-4.0 by Daniel Voigt Godoy([Dosovitskiy 2020]のFig.1にも構成図)
ViTの大きさ
- オリジナルの論文には大きさの異なる複数のモデル
- ViT-Base: 層の数12、ベクトルの次元: 768、パラメータ数: 8600万
- ViT-Large: 層の数24、ベクトルの次元: 1024、パラメータ数: 3.07億
- ViT-Huge: 層の数32、ベクトルの次元: 1280、パラメータ数: 6.32億
トークンに対応するベクトルの作り方
- 画像を
- 例:
- 3はチャンネルの数(RGB)
- 位置の埋め込みも行う
- ただし固定値ではなく、パラメータは学習対象
- 例:
- 画像の理解
- 局所的な理解: ベクトルの中
- 大域的な理解: 自己注意機構で学習
事前学習の方法
- 教師あり学習で分類問題を解く
- 言語と違って教師なし(BERTのような穴埋め)はあまり効果がない
- オリジナルの論文で用いられた訓練データ
- JFT-300M
- 3億枚の画像、18291クラスのデータセット
- ImageNet-21k
- 1400万枚の画像、21841クラスのデータセット
- JFT-300M
- 訓練データが多いと高い性能を発揮(JFT-300Mのほうがよかった)
ViTの機能のしかた
- 位置の埋め込みに関して
- [Dosovitskiy 2020]のFig. 7左
- 画像処理で使われる基底関数のようなものができている
- どこを見て判断しているか
- [Dosovitskiy 2020]のFig. 6、Fig. 7右
- 自己注意機構のヘッド(マルチヘッド注意機構のヘッド)には、入力に近い層ですでに大域的なものとローカルなものなどバリエーションが出る
- 大域的なものはCNNの入力に近い方のたたみ込み層に類似
- 入力から遠ざかるとより大域的に
Image GPT[Chen 2020](サイト)(動画)
- GPTの画像版
- GPT-2の構造を使用
- パラメータ数: iGPT-Lというモデルで
- 画像を途中まで入力して、次の画素を当てさせる
- PixelCNNと同じ問題
- GPT同様、ヘッドをつけてファインチューニングすると他のタスクに利用可能
Image GPTの学習
- 2種類の訓練方法
- 次の画素の予測(GPT的)
- 穴埋め問題(BERT的)
- 埋め込みに相当するベクトル: 画像の解像度を下げて1列に並べたもの
- サイト:
- 論文:
- サイト:
Diffusion Transformer(DiT)[Peebles 2022]
- 拡散モデル+Transformer
- さらに潜在空間に情報を圧縮する潜在拡散モデルも使用
- ラベルを入力して出力をコントロール(分類器なしガイダンス)
- 構造
- [Peebles 2022]の図3
- 入力: 画像のトークンの他、ラベルを表すベクトルと時刻を表すベクトルを足したトークン1つ
- 後者はadaLN-Zeroという仕組みで画像に作用させる
- FiLMにもうひとつパラメータを足したようなもの
- 後者はadaLN-Zeroという仕組みで画像に作用させる
- 出力: 画素ごとのノイズの平均値と分散
- 入力: 画像のトークンの他、ラベルを表すベクトルと時刻を表すベクトルを足したトークン1つ
- 画像のサイズを落とすためにVAEを使用
- [Peebles 2022]の図3
CLIP(Contrastive Language-Image Pre-training)[Radford 2021]
- contrastive: 「対照的な」という意味
- 対照学習(あとで説明)でテキストと画像を結びつけ
- 図
- CLIPでできること
- 画像に何が写っているかを認識(ある意味ではラベルの数に制限がない)
- テキストから画像を生成するときの部品
- unCLIP(あとで扱います)
CLIPに関する背景
- よく行われてきた画像認識の方法の手順
- 写真をあつめる
- 写真に写っているものをラベル付けする
- 学習
- 上記方法の問題
- めんどくさい
- ラベルのあるものしか認識できない
ラベル(ではなくキャプション)のついた画像の収集
- 画像にはキャプションのついたものがある(論文はそうですよね?)
- 原論文: 4億組の画像とキャプションのセットを収集
- 問題: キャプションは単語ではなく文や句になっている
- 単純なラベルではない
CLIPの学習方法
- 前ページの方法で学習用のデータを準備
- ViTを使って画像をエンコーディング
- Transformerを使って文をエンコーディング
- エンコーディングされたデータ(埋め込み)同士の相関を学習
- 補足: 必ずしもViT、Transformerである必要はない(が、Transformerを使ったほうが性能が高くなる)
CLIPの構造
- p.12の図
- image encoder: ViT
- 入力は画像
- クラストークンを出力として使う(数百次元のベクトル)
- text encoder: Transformerのデコーダから交差注意機構を除いたもの
- 入力は画像のキャプション
- 出力のフォーマットをimage encoderの出力に合わせる
- 数理的に重要な点: マルチモーダルであること
- text encoderとimage encoderの出力が同じ潜在空間にプロットされる
- キャプション(文、句)と画像が同じ空間に配置され、似たものが近くに配置される
- text encoderとimage encoderの出力が同じ潜在空間にプロットされる
評価方法(対照学習、contrastive learning)
- image encoderの出力: ベクトル
- text encoderの出力: ベクトル
- image encoderの出力: ベクトル
- ペアとなっている画像とキャプションのベクトルを同じにしたい
- コサイン類似度:
- コサイン類似度:
- ペアでない画像とキャプションのベクトルを違うものにしたい
学習したモデルの使い方
- 例: 画像の分類
- 分類したいものに対してラベルを
- 「a photo of <ラベル>」という句を
- 画像をimage encoderに通して特徴ベクトル
- 分類したいものに対してラベルを
DALL·E(ダリ)[Ramesh 2021]
- 句や文から画像を生成
- Transformerに、文章の続きとして画像を考えさせる
- 使うもの
- Transformer(デコーダ)
- GPT-3の改造版
- 画像も埋め込みベクトルにして入力できるように
- VQ-VAE(論文ではdiscrete VAE(dVAE)といっている)
- Transformer(デコーダ)
DALL·Eの学習
- キャプションと画像がペアになったものを訓練データに
- CLIPと同じ
- Stage 1: 集めてきた画像を使ってdVAEに学習させる
- 学習済みのデコーダに符号列を入力すると画像が生成されるように
- Stage 2: 入力文の後ろに符号列を生成するようにTransformerを学習
DALL·Eによる画像の生成
- 前ページステージ2の構成で
- https://openai.com/ja-JP/index/dall-e/ のサイト
- 512枚の画像を生成して、CLIPでランク付けして上位32枚を出力
- 遊んでみましょう
- https://openai.com/ja-JP/index/dall-e/ のサイト
GLIDE[Nichol 2021]
- Guided Language to Image Diffusion for generation and Editingの頭文字
- generationがかわいそう
- 「言語で誘導された画像の生成、編集のための拡散モデル」
- 自然言語+分類器なしガイダンスで拡散モデルに画像を生成させる
- (他、「CLIPガイダンス」も試されたが分類器なしのほうが結果がよかった)
- 自然言語をエンコードしたものを分類器なしガイダンスのラベルに利用
- 構造はU-Net
- 生成される画像: 論文の図1
- ファインチューニングで画像の一部をテキストで改変できる(image inpainting): 論文の図2, 3, 4
DALL·E 2(公式の動画)
- DALL·Eの後継
- 基本的なアイデア
- CLIPを使う
- テキストと画像が同じ潜在空間にいるので、
潜在空間のベクトル- ただし、整った画像を出力するためにいろいろ工夫
構造
- 点線の上: CLIP(学習のときに使う)
- 点線の下: 生成の部分
- 事前モデル(prior)とデコーダ(ほぼGLIDE)で構成
事前モデル+デコーダ(unCLIP[Ramesh 2022])
- テキスト
- 数式上は冗長だが学習のときにヒントが増えて質が向上
- 最後の項:
- 後ろの確率分布: 事前モデル
- 質の高い画像の特徴ベクトルを出力
- 単にテキストの特徴ベクトルを出力するのではなく、テキストも入力して強化
- 前の確率分布: デコーダ
- こちらもテキストを再度入力
- 後ろの確率分布: 事前モデル
Stable Diffusion
- サービスのサイト: https://stablediffusionweb.com/ja
- DALL·Eシリーズのライバル
- 使いやすくて一気に普及
- 50億枚の画像を訓練に使用
Stable Diffusion(v1)の構造(Latent Diffusion Models、LDM)[Rombach 2021]
- [Rombach 2021]の図3(Wikipediaに掲載されている図)
- 上部の
- 訓練画像を潜在空間のベクトルに変換してからDDPMで拡散
- 潜在空間: [Esser 2020]で提案されたVQGANのもの
- 要はVQ-VAEのGAN版
- 図中のピンク色の部分がVQGAN(の変種)
- 潜在空間: [Esser 2020]で提案されたVQGANのもの
- 訓練画像を潜在空間のベクトルに変換してからDDPMで拡散
- 下部の
- ノイズを潜在空間のベクトル
- テキストや画像の埋め込み(図の白枠内で生成)によるガイダンスを交差注意機構で行う
- 基本、行列の計算なのでU-Net内にも組み込める
- ノイズを潜在空間のベクトル
- 上部の
まとめ
- 言語処理の技術の画像への転用や画像処理との組み合わせを勉強
- この間にもどんどん最新のサービスがリリースされている
- 新しい技術も開発されている
- 扱っていないもの: 動画の理解や動画の生成