答えの例2
- 要素が1つだけ1になるので「ワンホットベクトル」と呼ばれる
問題: 微妙なときに言い切っちゃっていいの?
答えの例3
猫 犬 そ れ 以 外
- 識別用のANNの出力はこの形式が一般的
- ひとつに決めたければ確率最大のものを選択
もうひとつ問題
- 学習のときの損失関数はどうする?
- 前ページの例3で考えてみましょう
- 出力:
- 正解:
- 正解については、正解に対応する要素
- 正解については、正解に対応する要素
一般的な答え
- 交差エントロピーを使用
- 数学好きな人への補足: カルバック・ライブラー情報量を最小化するのと等価
- 正解に対する確率が高い場合(例:
- 答えは省略
以前から触れていた話題
- 動物は視覚をどう行動や判断に必要な情報に変えているか
- それをコンピュータで再現できるか
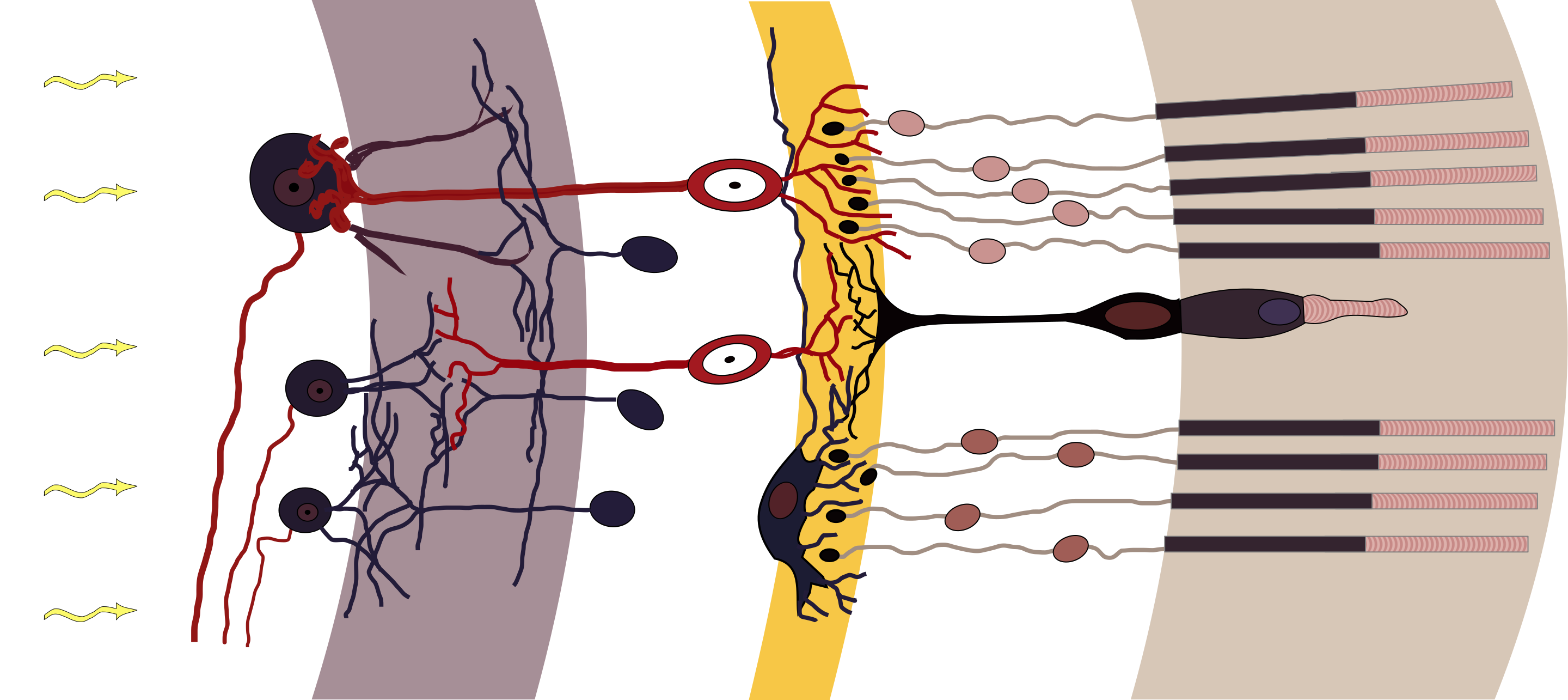 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Retina-diagram.svg, by S. R. Y. Cajal and Chrkl, CC-BY-SA 3.0)
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Retina-diagram.svg, by S. R. Y. Cajal and Chrkl, CC-BY-SA 3.0)
人工ニューラルネットワーク(ANN)でできる?
もうひとつの話題: なんか自動で絵を描くやつが出現
- 実例は世の中に氾濫しているので各自調査を
- こいつらはどういう仕組み?
視覚・画像とANN(CNN)
- 映像、画像の特性に特化したANNが存在
- 画像の特性
- 2次元(深度があれば3次元、動画でも時間軸を入れると3次元)
- ある画素の周囲に似た画素がある
- 画像の特性
- おさらい: ディジタル画像
- 平面が格子状に分割されて、数字の大小で色の濃さが表される
(例: 右図。数字はてきとう) - カラーの場合はR、G、Bそれぞれについて格子状の数値データ
- 平面が格子状に分割されて、数字の大小で色の濃さが表される
画像認識の難しさ
- 同じものが大きく写ったり小さく写ったり回転して写ったり
- 変形したり抽象化されたりデフォルメされたり

CNN(convolutional neural network)
- テレビ局ではないです
- convolutional: 「畳み込みの」
- 画像の近いところの画素値を入力して
出力するニューロンを多用(右図)- 画像の近いところ:
- 小領域の画素の特徴や変化を出力
- さらに下の層でも畳み込みすることで全体の特徴を捕捉
- 画像の近いところ:
- 「畳み込み層」と他の層の組み合わせで画像を処理
CNNの部品1: 畳み込み層
- 画像の一部(n
- フィルタを1つずつずらして適用(右下図)
- 下流の画素数を変えたくない場合
- 2つ以上ずらすこともあり(ずらす量のことをストライドという)
- 下流の画素数を変えたくない場合
- 畳み込みの演算(下図)
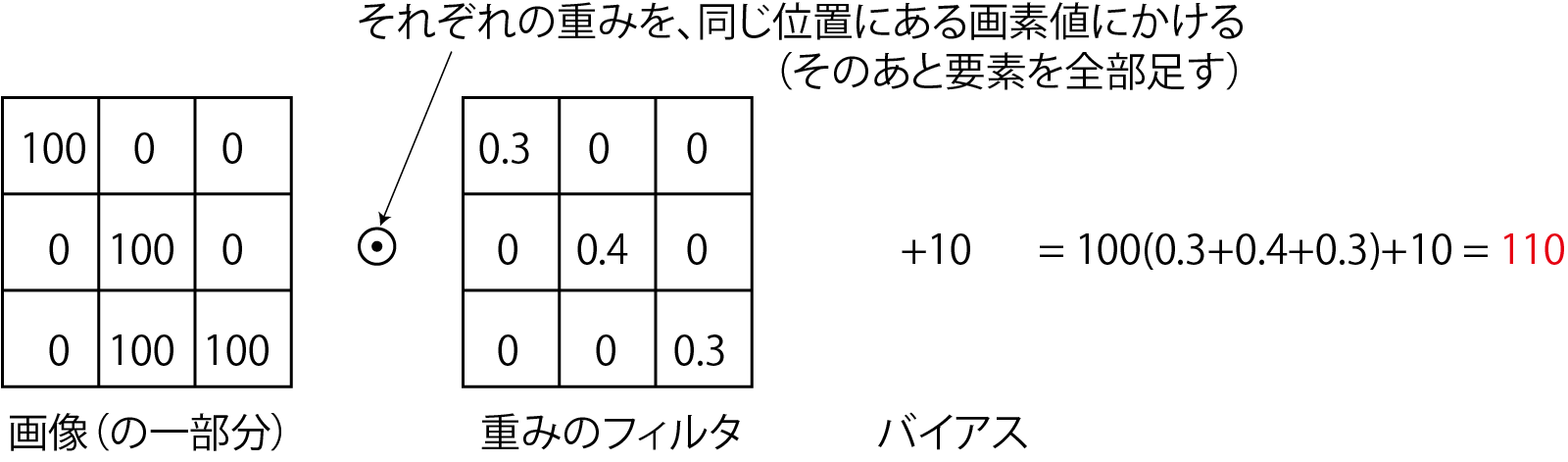
フィルタの意味
- フィルタ: 従来の画像処理に使われてきたものと同じ
- 局所的な特徴(エッジなど)を検出
- 畳み込み層の学習=フィルタの学習
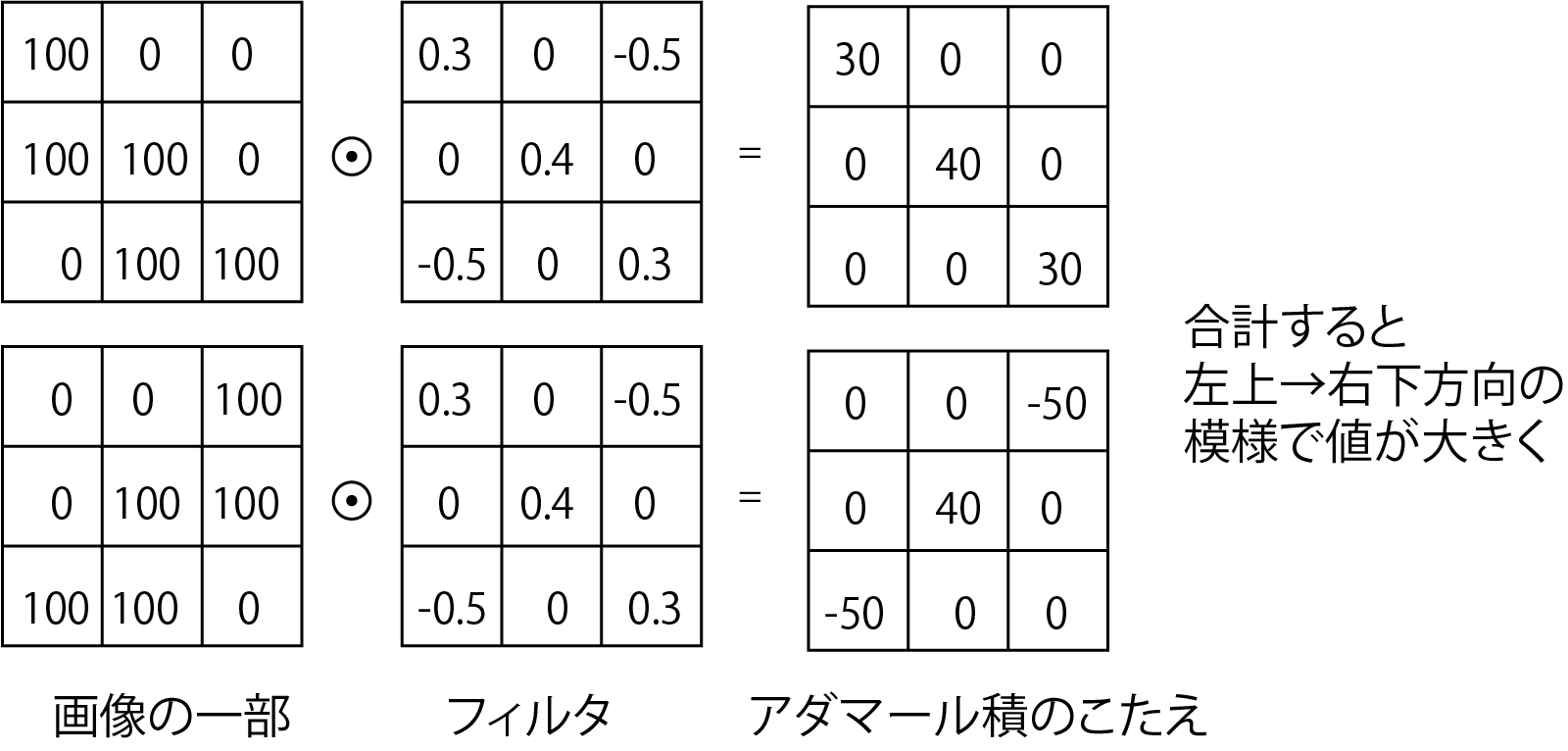
フィルタの計算式
- 前回までは
- 前回までは
- 2次元になっただけでこれまでと同じ
- ただし「全結合」ではない
- アフィン層(+活性化関数層)のことを「全結合層」ということがある
CNNの部品2: プーリング層(サブサンプリング層)
- 窓のなかで特徴の高い画素だけを残して画素数を減らす層
- 最大値を残す「maxプーリング」が主に使われる
- 学習はしない
- 画素が減って後段(ものを分類するネットワーク)が学習しやすく
- 写ってる物体の位置のズレに少し強くなる
- 冒頭の「難しさ」についてはCNNではそんなに解決できてないので学習で様々な大きさ、位置、向きの画像を使う
CNNの部品3: ソフトマックス層
(注意: CNN以外にも使われます)
- softmax(softな最大値): 1つに決めないということ
- 使用例: 画像に映ったものを判別
- 答えを断定せず確率で出力(例: 犬90%、猫9%、他1%)
- 実世界は微妙な場面が多いので、1つに決めないで曖昧に出力したほうが都合よい
- 数式
- 入力
- 入力
チャンネル
- カラー(RGB)画像を扱う場合
- 画素の縦横方向の他に3つの「チャンネル」を持つ
- 画素ごとにベクトルがあると考えても良い
- RGBそれぞれにフィルタを用意すると出力も3chに
- 画素の縦横方向の他に3つの「チャンネル」を持つ
- 1つのチャンネルに複数のフィルタも適用可能
- 下図LeNet[LeCun1989]の構造(画像: Zhang et al. CC BY-SA 4.0)
- 画像から手書きの数字を識別するCNN(1ch
- 画像から手書きの数字を識別するCNN(1ch
- 下図LeNet[LeCun1989]の構造(画像: Zhang et al. CC BY-SA 4.0)
代表的なCNN
- LeNet: 前ページの構成で手書き文字を識別
- 畳み込み・プーリング
- シグモイド関数を活性化関数に使用
- 畳み込み・プーリング
- AlexNet: 畳み込みを5層に深く
- 右図: LeNet(左)とAlexNet(右)の比較
- LeRUを活性化関数に使用
- 1000種類の識別
- AlexNetの論文
- 学習した中間層や認識結果が見られる
CNNのまとめ
- 畳み込み層で模様の特徴を抽出
- LeNet、AlexNet: 画像から物体を識別
- CNNにはさらなる用途が
U-Netと潜在空間
- U-Net: CNNの後ろに逆向きのCNNをつけたもの
- 当初の用途: セグメンテーション
- 画像に写っているものごとに画像の領域を分割
(右図: [三上他 2022])
- 画像に写っているものごとに画像の領域を分割
- 当初の用途: セグメンテーション
- 「逆向きのCNN」
- 「転置畳み込み(後から説明)」という操作で画像を大きくしていく(構造は次ページ)
U-Netの構造
- 左半分: CNN(物体の識別のような処理)
- 右半分: 逆向きのCNN(識別結果からの画像の構築)
- スキップ接続を使用
- 途中で次元が落ちているので単なる差分学習以上の意味
 画像: Mehrdad Yazdani, CC BY-SA 4.0
画像: Mehrdad Yazdani, CC BY-SA 4.0
転置畳み込み
- 画像の解像度を上げる操作
- 画像をパディングして大きくし、フィルタを適用
- この操作とスキップ接続で得た元の画像の情報からセグメンテーション
- 画像をパディングして大きくし、フィルタを適用
- U-Netについての説明はこれで終わりだが、単にセグメンテーションができる以上にこの構造は重要
オートエンコーダと潜在空間
オートエンコーダ
- 入力と出力を一致させるように学習されたANN [Hinton 2006]
- 損失関数: 入出力の平均二乗誤差(MSE, mean square error)
- 学習のためのラベル付けは不要(教師無し)
- 構成はCNNでも全結合でもよいが、U-Net状に中間の次元を小さく
- 入力側: どんどん情報を落としていく
- 出力側: どんどん情報を増やしていく
- 疑問: 何の意味があるの?
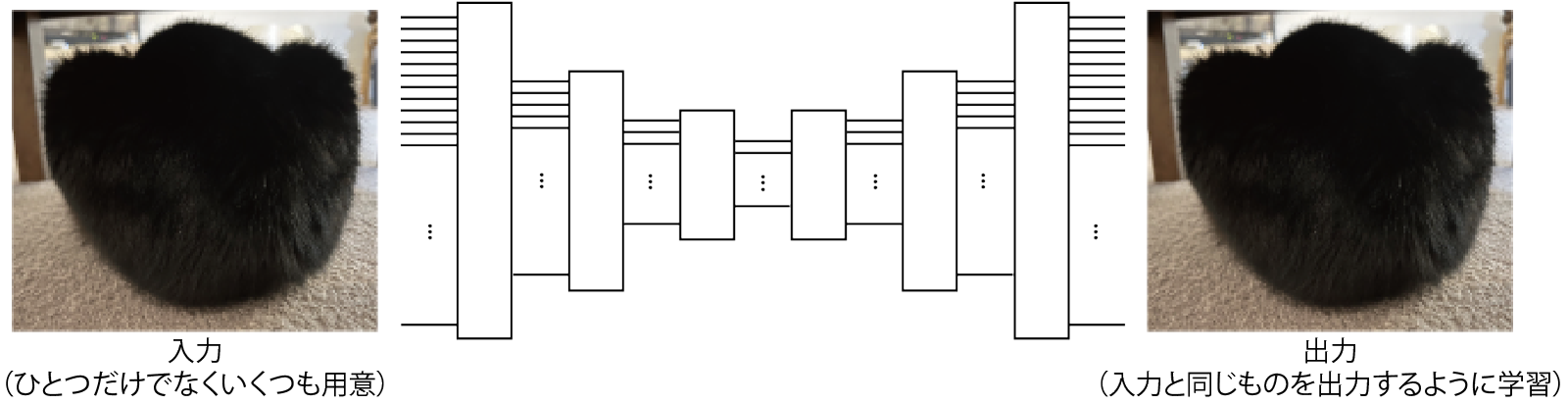
- 損失関数: 入出力の平均二乗誤差(MSE, mean square error)
入力側(エンコーダ)のやっていること
- 入力されたデータの分類
- (学習がうまくいった場合は)似たような画像から似たような出力が得られる
- うしろに全結合層(とソフトマックス層)をくっつけて追加で学習させると分類器に
- 右図の例: 出力を2次元まで縮小した場合の
出力の分布の例
(注意: 実用的なものはもっと高次元)- 分布している空間を潜在空間と言う
出力側(デコーダ)のやっていること
- 潜在空間のベクトルからデータを復元
- 例: 「犬」のベクトルが来たら犬の写真や絵を描画
- 復元方法(絵の描き方)を学習
- 転置畳み込みのフィルタなどのパラメータに
- 復元しやすいようにエンコーダ側が学習される
- 潜在空間でのベクトルの分布が決まる
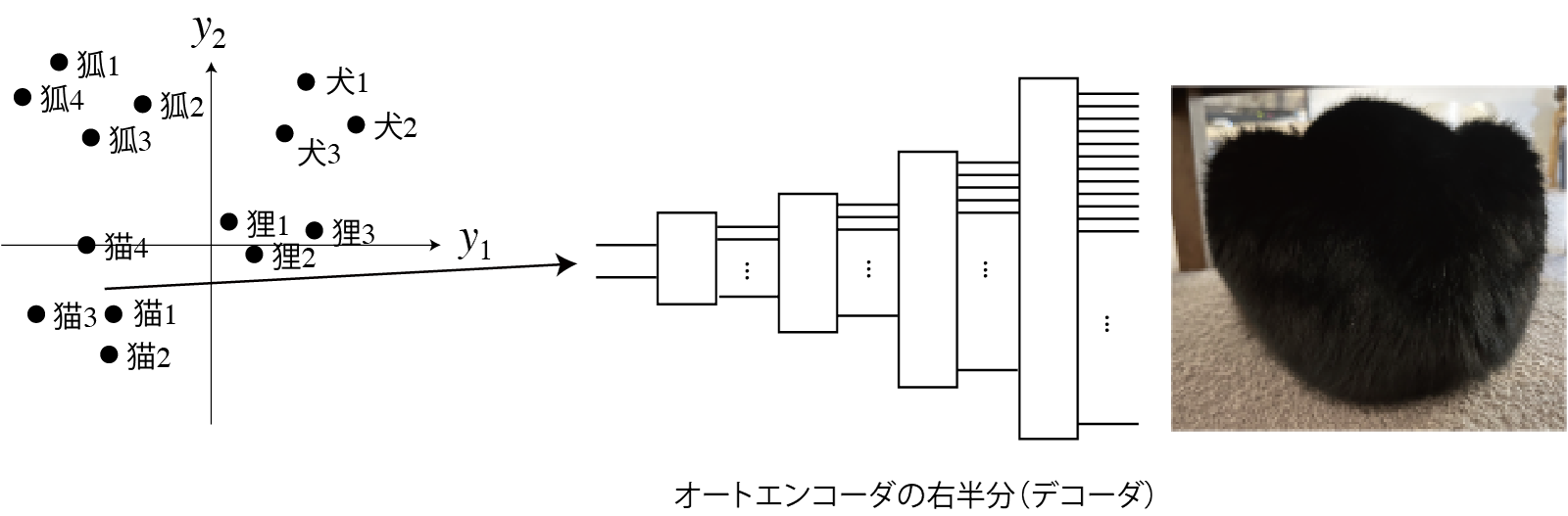
オートエンコーダの利用
- エンコーダとデコーダを分離して利用
- エンコーダ
- 先に前結合層などを取り付けて分類器に
- 先に別のデコーダを取り付けると別のものが生成される
- デコーダ
- 学習に用いたもの以外のエンコーダを取り付けると変換器に
- 例「犬」と入力
- 例「犬」と入力
- 学習に用いたもの以外のエンコーダを取り付けると変換器に
まとめ
- CNNからオートエンコーダまで学習
- 画像の識別から生成までの流れを見てきた
- CNNによる物体の識別: エンコーダ+識別器
- U-Netによるセグメンテーション: オートエンコーダに似た構造
- 次回以降にいくつかの応用
- 台形の図がよく出てくる
- 画像の識別から生成までの流れを見てきた